東広島市居住支援協議会設立記念講演会の開催について
令和7年5月16日、東広島市では、低所得者・高齢者・障がい者など、住宅の確保に配慮が必要な方々が安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、「東広島市居住支援協議会」を設立しました。これを記念して開催された講演会には、約180名の参加者が集まり、盛況のうちに終了しました。
講演では、令和7年10月1日施行の住宅セーフティネット制度改正について、その背景と内容が説明され、今後、住まいにお困りの方々への一体的な支援体制の整備や大家・不動産関係者が安心して住宅を提供できる市場環境の整備の必要性が示されました。
参加者アンケートからは、協議会への期待として、「地域に根ざした支援体制の整備」「市民への啓発活動の強化」「多様な関係者の連携」など、実践的かつ継続的な取り組みを求める声が多数寄せられました。
今後、東広島市居住支援協議会では、制度と地域の実情を踏まえながら、誰もが安心して暮らせる住生活の実現に向けて、行政・福祉・民間が連携し、支援の輪を広げてまいります。
講演「住宅セーフティネット制度について」
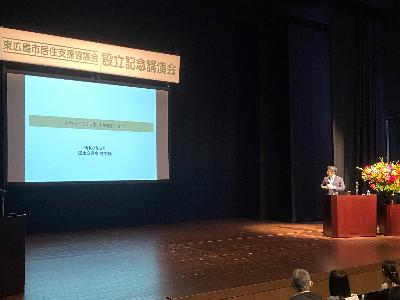
国土交通省住宅局安心居住推進課
居住支援協議会の設立は、地域の住まいの課題に向き合う新たなスタートです。人口減少や単身世帯の増加など、社会の変化に対応するためには、行政・福祉・住宅関係者が連携し、地域に根ざした支援体制を築くことが求められています。
今回の住宅セーフティネット制度の改正では、住宅確保要配慮者への支援強化が図られます。改正の柱は、(1)民間賃貸住宅の円滑な利用に向けた市場環境の整備、(2)入居中の見守り・安否確認などの支援を行う「居住サポート住宅」の導入、(3)住宅と福祉の連携による地域の居住支援体制の強化の3点です。これらの取り組みにより、安心して暮らせる住まいの選択肢が広がります。
このうち(3)「住宅と福祉の連携による支援体制の強化」は、まさに居住支援協議会を活用した取り組みです。協議会は、行政・福祉・住宅関係者が課題を共有し、地域の実情に応じた支援策を協議・実践する場として、制度の実効性を高める役割を担っています。
居住支援協議会は、「人」と「物」、そして地域資源を最大限に活用した取り組みを発展させ、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に向けた継続的な協議と実践の場として、今後ますます重要な役割を果たしていくことが期待されています。
基調講演「居住支援からはじまるまちづくり~みんなが安心して暮らせる地域を目指して~」
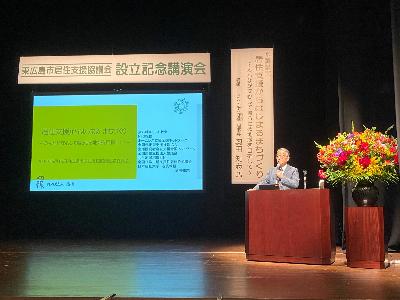
奥田知志氏(NPO法人抱樸理事長)
日本社会は今、「再創造」の時代を迎えており、居住支援協議会はその最前線として、地域に根ざした支援のあり方を創造する場となります。
居住支援とは、単に「家を確保する」ことだけではありません。家を得ても、孤立してしまえば生活は成り立ちません。支援の本質は、「人とのつながり=ホーム」を築くことにあります。
居住支援は、「ハウスレス問題:家・仕事・お金など物的な困窮」と「ホームレス問題:人間関係の喪失、孤立の状態」の両方の課題に対応する支援です。家があっても、誰も訪ねてこない、誰にも看取られない――そんな状況を防ぐために、地域の支え合いが必要です。
講師の実体験から、支援者が「お客さん」として定期的に訪問することで、生活に変化が生まれることが語られました。掃除をする、食器が増える、誰かが来ることを待つ――それは「社会化された生活」の始まりです。
このような関係性の支援は、大家さんの安心にもつながります。誰も来ない人には貸しづらいが、地域の支援があるなら安心して貸せるようになります。
住宅セーフティネット法と生活困窮者自立支援法が改正され、居住支援と福祉支援の連携が強化され、居住支援法人と生活困窮者相談窓口の連携が制度上明記されました。
また、ICTを活用した見守りや、家賃債務保証制度、代理納付制度など、大家・入居者・地域の安心を支える仕組みも進化しています
現在、日本の世帯の約4割が単身世帯。かつての「家族で支える」社会モデルは限界を迎えています。家族機能の喪失により、気づき・つなぎ・見守りの役割を地域が担う必要があります。
居住支援協議会は、住宅政策の枠を超え、地域全体で「住生活」を支える仕組みづくりを進める場です。
一人ひとりが安心して、最後まで住み慣れた地域で暮らし続けられる社会の実現に向けて、みんなで考えていくのが、居住支援協議会の役割です
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
メールでのお問い合わせ
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-












更新日:2025年08月21日