国保で受けられる給付
療養の給付(医療費の7~8割を国保で負担)
病気やけがで医療を受けるとき、資格確認書の提示または保険証登録したマイナンバーカードの利用により、医療費の7~8割を国保が負担します。
| 0歳~小学校就学前 | 2割負担 |
| 小学校就学後~70歳未満 | 3割負担 |
| 70歳以上 | 2割負担 (現役並み所得者3割) |
入院中の食事代
入院中の食事代は、一部(標準負担額)を支払うだけで残りは国保が負担します。
療養病床に入院する65歳以上の人は居住費の負担が必要になります。
一部負担金の減免
特別な事情がある場合において病院での一部負担金の支払いが著しく困難と認められるときは、申請により減免の適用を受けられる場合があります。
詳しくは国保年金課にご相談ください。
療養費の支給(医療費を全額支払ったとき)
いったん医療費を全額自己負担した後であっても、次のような場合は、市の窓口に申請し療養費の払い戻しを受けることができます。
次のすべての申請に、次の2点が必要となります。
- 振込先口座のわかるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)、または個人番号が確認できる書類と本人確認書類
|
こんなとき |
申請に必要なもの |
|
不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けたときや、旅先で急病になり保険資格が確認できるものを持たずに診療を受けたとき |
|
|
手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合) |
|
|
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
|
|
骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔整整復師の施術を受けたとき |
|
|
国保を扱っていない施術所で、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要) |
|
|
海外渡航中に治療を受けたとき ※ただし、以下の場合は支給されません。
|
|
高額療養費の支給
医療機関で支払った一部負担金(食事代等、保険対象外の自己負担分を除いた額)が限度額を超えた場合、申請により高額療養費として後から支給されます。
詳しくは、下記のリンクをクリックして下さい。
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
詳しくは、下記のリンクをクリックして下さい。
葬祭費
国保加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に3万円支給されます。市役所の国保年金課または各支所・出張所で申請してください。
葬儀を行った日の翌日から起算して2年以内に申請してください。
申請に必要なもの
- (お持ちの方のみ)亡くなられた国保加入者の資格確認書(世帯主が亡くなられた場合は、同じ世帯の国保加入者全員の資格確認書)
- 振込先口座のわかるもの
- 葬儀をした人を確認できるもの(埋火葬許可証、会葬御礼状又は葬儀費用領収書(費用を支払った人の氏名がフルネームで記載されているもの))
ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座が必要です
資格喪失の届出に必要なもの
葬祭費の支給申請と亡くなられた方の資格喪失の届出は、同時に行っていただく必要があります。
資格喪失の届出には、亡くなられた方の個人番号と届出時の世帯主の個人番号の記載が必要で、確認書類として次のものが必要です。
- 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 届出時の世帯主の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
他の健康保険の被保険者だった人が、資格喪失後3か月以内に死亡した場合は、その健康保険から埋葬料(5万円)の支給を受けることができます。詳しくは、元勤務先または健康保険組合等にお問い合わせください。
移送費
移動が困難な方で、医師の指示により緊急やむを得ず転院したときなどは、国保が必要と認めたときに移送に要した費用が支給されます。市役所の国保年金課または各支所・出張所で申請してください。
申請に必要なもの
振込先口座のわかるもの、医師意見書、領収書、世帯主及び受診者の個人番号がわかるもの、来庁者の本人確認書類
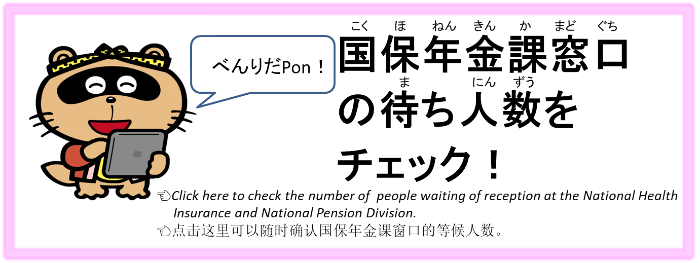
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
メールでのお問い合わせ
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-












更新日:2025年08月01日